
2019年10月11日記
演出:五戸真理枝
出演:立川三貴 / 廣田高志 / 高橋紀恵 / 瀧内公美 / 泉関奈津子 / 堀文明 / 小豆畑雅一 / 伊原農 / 鈴木亜希子 / 谷山知宏 / 采澤靖起 / 長本批呂士 / クリスタル真希 / 今井聡 / 永田涼 / 福本鴻介 / 原金太郎 / 山野史人
ゴーリキーの戯曲『どん底』、書かれたのは1902年冬〜1903年の春。
時期的にいって、社会主義国家が生まれる直前。
当方、1980年に高校を卒業。ソ連の消滅は1991年12月。
公教育のすべてを冷戦時代に受けているのに、「ゴーリキー」をまったく読んだことがなかった。
むろん、演劇も見たことない。
おそらく上演回数は相当に多いと思われる。
演出によって、いくらでも暗い、陰気な舞台になりそう。
実際、1954(昭和29)年4月「芸術新潮」に
私の腑に落ちない点は、日本の「どん底」は、なぜこんなにじめじめしてゐて暗く、やりきれないほど「長い」か
という一文が載ったらしい。(「岸田國士 『どん底』の演出」)
ゴーリキイが、この作品のなかで、しばしば、時は「新春」だといふことを見物に想ひ出させようとしてゐるのは、それと関係はないだらうか? 象徴とはさういふものではないか。強ひてイデオロギーの有無に拘泥しなくても、戯曲「どん底」は、長い北欧の冬からの眼醒めを主題とする希望と歓喜の歌が、この、辛うじて人間である人々の胸の奥でかすかに響いてゐるやうな気がする。ゴーリキイは、「どん底」の人々の誰よりもスラヴ的「楽天家」なのである。
ともあった。
「明るい」「春」「希望と歓喜」「楽天家」
そこまで言う演出家もいれば、ジメジメさせる演出家もいたってことだ。
さて今回の『どん底』、ジメジメして暗い、ということはなかった。どっちかというとサバサバしていた。
ちょっとした仕掛けがあって、劇中劇になっている。
まず出だし。会社員風の女性が嬉しそうに走ってきて服を着替える。
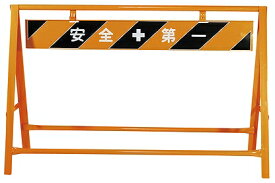
↑道路工事現場でよくみかける「バリケード」。これにOLスーツ服をかけ、巻きスカートとエプロンに着替え、ロシアの女将風に変身。そして、たたたと駆け上がって、演劇仲間達と集合。
「これから『どん底』やるぞー」と皆で盛り上がる。
ちなみにこの女性が扮するのはクワシニャーといって、中年の肉饅頭売りの、威勢のいい女性。
そんな感じで進行するから、鉄パイプや木パレットやコンテナで舞台が作ってある。

↑木パレット
新国立劇場の舞台美術の人なら、おちゃのこさいさいで、1900年のロシアの「木賃宿」作れるだろうに、工事現場の見慣れた物品を使っているのが味噌。
そして、皆で一生懸命「どん底」の演劇空間を作り上げていく。
その中での『どん底』をどう味わうか、どう受け止めるかと。
劇中劇とはいっても劇は劇なので、貧しいなあ、不幸なんだなあと、感じないわけにはいかなかった。
それに飛び交う罵声が本当に罵声で、つらいなあと。
アンナという女性が弱り切って横たわっていた。不幸だった。本人も「生まれてから死ぬまでずっと不幸だった」と直球を投げていた。
ルカという、この共同体の中では客人的立場のおじいさんがアンナの話を聞いて慰めていた。
ルカが、このフラットな関係の中で一番目立っているっちゃ目立っている。服装も日本の時代劇の着物を着込んできたりして。
今の時代って、ものすごく役に立つ言葉、メンタルに対して即効性のある言葉が喜ばれる。お悩み即解決みたいなやつとか。
ルカも、それに近い啓蒙的なポジティブな事を言う。のだけど、力強くはない。積極性がさほどない。断言的ではない。
なので、大きな影響力を持たないまま去って行く。ルカが何を言ったかというと「人はより良きもののために生きる」。
「より良きもの」がキーワード感あった。
ルカがいなくなるといかさま師サーチンがルカの口癖を真似るようになる。サーチンは威勢のいい男で、声がでかい。口も巧い。
であれこれ言ったあげく、橋桁みたいなコンクリートに大きく「人 間」と書く。
「人 間」と書きながら色々言っていたが、全体に嘘くさい。
そうこうしている間に
彼、彼女らの演じる『どん底』はクライマックスを迎える。
この時、「我々」「同志」としての連帯の歓びが沸き立つ。というか沸き立ちかける。沸き立ちかけて脱臼し、沸き立ちかけて頓挫し、沸き立ちかけて錯覚のようになる。
彼、彼女らは、「我々」「同志」としての連帯の歓びを頓挫させる、という演劇空間を成立させる。
という表現でよいのか、わからないが、今ふりかえって思うに、そんな感じなのだ。
それはちょっと寂しい感覚だった。そして、ホッともしていた。
それでも「人 間」という言葉がコンクリートに残った。
人
間
と。
劇が終わって新国立劇場を出ると、目の前に70歳近い男性が歩いていた。スーツとスニーカーの。
新国立劇場は初台駅と直結しているから、行き先は駅しかない。
この人は、この舞台に満足しただろうか?
この人も、くすぶるような寂しさを感じたのじゃないだろうか?
いやさ、それとも「元気」をもらったのだろうか?
まったく解らない。想像もつかない。
もしも話しをしたら、「あんなのゴーリキーじゃない」「あの頃の俺たちは、理想の社会主義国家を夢見ていたんだ」と言ったりするのだろうか?
いやいや、仮に思っていても、初対面相手に言うかどうか。
言わないだろうけど、聞いてみたかった。
どん底の登場人物
ミハイル・イワーノヴィッチ・コストゥイリョフ 54歳、木賃宿の亭主。 ワシリーサ・カールポヴナ コストゥイリョフの女房、26歳。 ナターシャ ワシリーサの妹、20歳。 メドヴェージェフ ワシリーサとナターシャの叔父、巡査、50歳。 ワーシカ・ペーペル 泥棒、28歳。 クレーシチ・アンドレイ・ミートリイチ 錠前屋、40歳。 アンナ クレーシチの妻、30歳。 ナースチャ 売春婦、24歳。 クワシニャー 肉饅頭売りの女、40代かっこう。 ブブノーフ 帽子屋、45歳。 サーチン 40代ぐらい。 役者 サーチンとほぼ同年輩。 男爵 33歳。 ルカ 巡礼者、60歳。 アリョーシカ 靴屋、20歳。 クリヴォイ・ゾーブ 荷かつぎ人足。 だったん人 荷かつぎ人足。「だったん人」とはタタール人の意、 ロシアにおけるイスラム教徒のこと。 ほかに、名もなく台詞を持たない浮浪人数人。